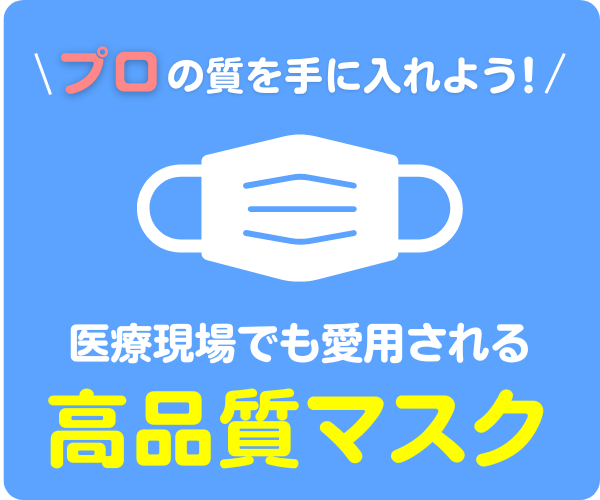介護の相談はどこにすれば良い? いざという時に役立つ相談先の例

少子高齢化が進む中で「自宅で在宅介護を行うことになった」という方も多くいらっしゃるでしょう。
介護が始まる際は、はじめてのことが多く、何をすれば良いのか悩んでしまうものです。自分一人でその悩みを抱え続けると、肉体的・精神的に負担がかかってしまいます。介護に関する悩みは、一人で抱え続けるのではなく、誰かに相談することが大切です。
ここでは、介護に関する悩みや疑問を話したり、質問したりできる相談先の例をご紹介します。
目次
介護の悩みは「地域包括支援センター」に相談するのがおすすめ

介護に関する悩みや疑問を相談したい時は、「地域包括支援センター」が基本の相談先になります。しかし、地域包括支援センターのことをよく知らないという方も多くいらっしゃるでしょう。
地域包括支援センターの概要は、以下のとおりです。
1. 地域包括支援センターとは?
地域包括支援センターとは、各市区町村に設置されている、高齢者のさまざまなサポートを行うための施設のことです。市区町村によっては「高齢者あんしんセンター」や「高齢者相談センター」「高齢者支援センター」など、異なる名称で呼ばれている場合もあります。
2023年4月時点で、全国に5,431カ所(ブランチ・サブセンターを含め7,397カ所)設置されていて、介護に限らず、高齢者の生活全般に関する悩みを無料で相談することが可能です。※1
2. 地域包括支援センターの役割
地域包括支援センターでは、ケアマネージャーや保健師(看護師)、社会福祉士といった専門スタッフに、介護や医療、暮らしの支援など、高齢者のさまざまな悩みを相談することができます。
具体的な地域包括支援センターの役割は、「総合相談」「介護予防ケアマネジメント」「権利擁護」「包括的・継続的ケアマネジメント」の4つです。
【総合相談】
地域包括支援センターは、介護に関する包括的な窓口です。高齢者のさまざまな悩みに対して、サービスや制度の紹介、アドバイスの実施といった対応を行います。
【介護予防ケアマネジメント】
要支援・要介護状態になる可能性のある方に対して、介護予防ケアプランの作成を行います。
【権利擁護】
高齢者が安心して暮らせるように、成年後見制度の活用促進や高齢者虐待への対応など、さまざまな権利を守るサポートを行うのも、地域包括支援センターの役割です。
【包括的・継続的ケアマネジメント支援】 「地域ケア会議」などを通じた自立支援型ケアマネジメントの支援や、ケアマネージャーへの日常的な個別指導・相談を行い、高齢者をサポートする体制を整えます。
介護をはじめ、医療や福祉に関しても対応しているので、迷った時は地域包括支援センターに相談してみてはいかがでしょうか。
3. 地域包括支援センターの利用の仕方
地域包括支援センターは、その地域に住む高齢者の方や、高齢者を支援している方なら、誰でも無料で利用できます。センターごとに管轄する地域が決まっているので、居住している地域を管理する地域包括支援センターに相談しましょう。
支援者と、対象となる高齢者が別々の場所で暮らしている場合は、対象となる高齢者が住んでいる地域の地域包括支援センターを使用する点に注意が必要です。
例えば、支援者が東京都、対象となる高齢者が千葉県に居住している場合は、千葉県の地域包括支援センターに相談します。
また、直接出向くのが難しい時は、電話で相談することも可能です。
どこの地域包括支援センターに相談すれば良いのかは、市区町村の担当窓口に問い合わせるか、厚生労働省のホームページなどからご確認ください。※2
その他の介護の相談先

地域包括支援センター以外にも、介護に関するさまざまな悩みを相談できる場所はいくつかあります。複数の相談先を知っておくと、いざという時に役立つでしょう。
介護などに関する主な相談先の例と、それぞれの特徴や使い方などをご紹介します。
1. 市区町村の相談窓口
要介護認定の申請や介護保険制度の手続きなどは、市区町村の役所で行います。
そのことからもわかるように、市区町村の役所に設置されている相談窓口で、介護に関するさまざまな相談を行うことが可能です。
相談に関しては、役所が管轄する地域に住んでいる方なら誰でも行えます。
役所の窓口なら、相談内容に応じて、適切な相談先を紹介してもらうこともできます。役所での申請が必要な場合は案内をしてくれるなど、スムーズに申請や手続きを進めやすい点もメリットです。
健康相談窓口や高齢者支援、福祉課など、地域によって相談窓口の名称は異なる場合があるため、自治体のホームページで確認するか、わからない時は総合窓口で訪ねてみると良いでしょう。
2. 医療機関
病気やけがなどで通院・入院している場合は、医療機関で相談できる場合もあります。入院中はもちろん、退院後の介護に関する悩みなども相談することが可能です。
通院している医療機関なら、体の状態に合わせて適切なアドバイスを受けることができます。
ただし、病院によっては相談に予約が必要な場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
かかりつけ医がいる方は、医師に訪ねてみるのもおすすめです。
3. 地域の民生委員
地域の民生委員に相談するのもおすすめです。民生委員とは、担当地域の介護や子育てなどに関する相談・支援を行っている、厚生労働大臣から委託された地域のボランティアのことです。
担当する地域のことを深く知っており、福祉やボランティアに理解がある方が、民生委員として活動しています。地域包括支援センターや医療機関よりも身近な相談相手として、介護をはじめ、日常生活に関するさまざまな悩みを話すことができます。
民生委員なのかわからない時は、自治体のホームページで検索してみたり、福祉課の窓口で聞いたりしてみると良いでしょう。
4. 電話相談
自治体によっては、「高齢者安心電話」のような電話サービスを実施しているケースもあります。日常生活の悩みごとを、気軽に相談することが可能です。管理栄養士や介護福祉士など、専門職の方からアドバイスを受けたり、財産のような法律に関する相談をしたりできる場合もあります。
各地でさまざまな電話相談が実施されているので、窓口に出向くのが難しい時は利用してみてはいかがでしょうか。
認知症に関する相談はどこにすれば良い?

また、かかりつけ医や通院している医療機関、最寄りの認知症疾患医療センターで相談してみるのもおすすめです。
医療機関の受診には予約が必要な場合もあるため、詳細は各医療機関のホームページなどでご確認ください。
悩みがある時は気軽に相談してみよう

介護は、精神的・肉体的に負担がかかりやすいものです。突然同居人の介護を行うとなると、初めてのことが多く、どうすれば良いのか悩んでしまうこともあるでしょう。
介護に関する悩みを相談できる窓口は、地域包括支援センターや市区町村の役所など、数多くあります。介護に関する悩みや不安がある時は、一人で抱え込むのではなく、気軽に相談してみてはいかがでしょうか。