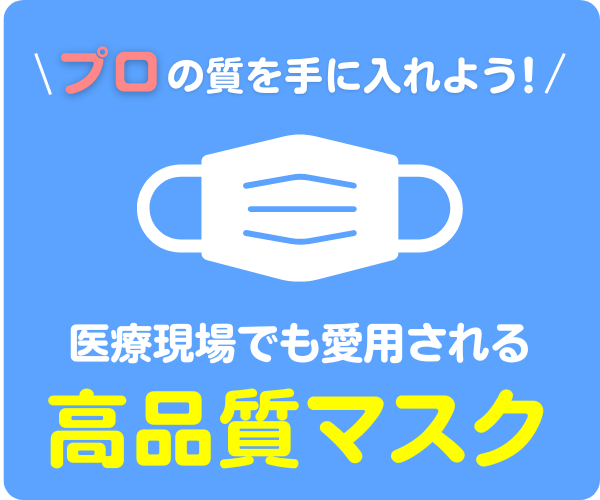早めの行動が大事! 個人でもできる花粉対策
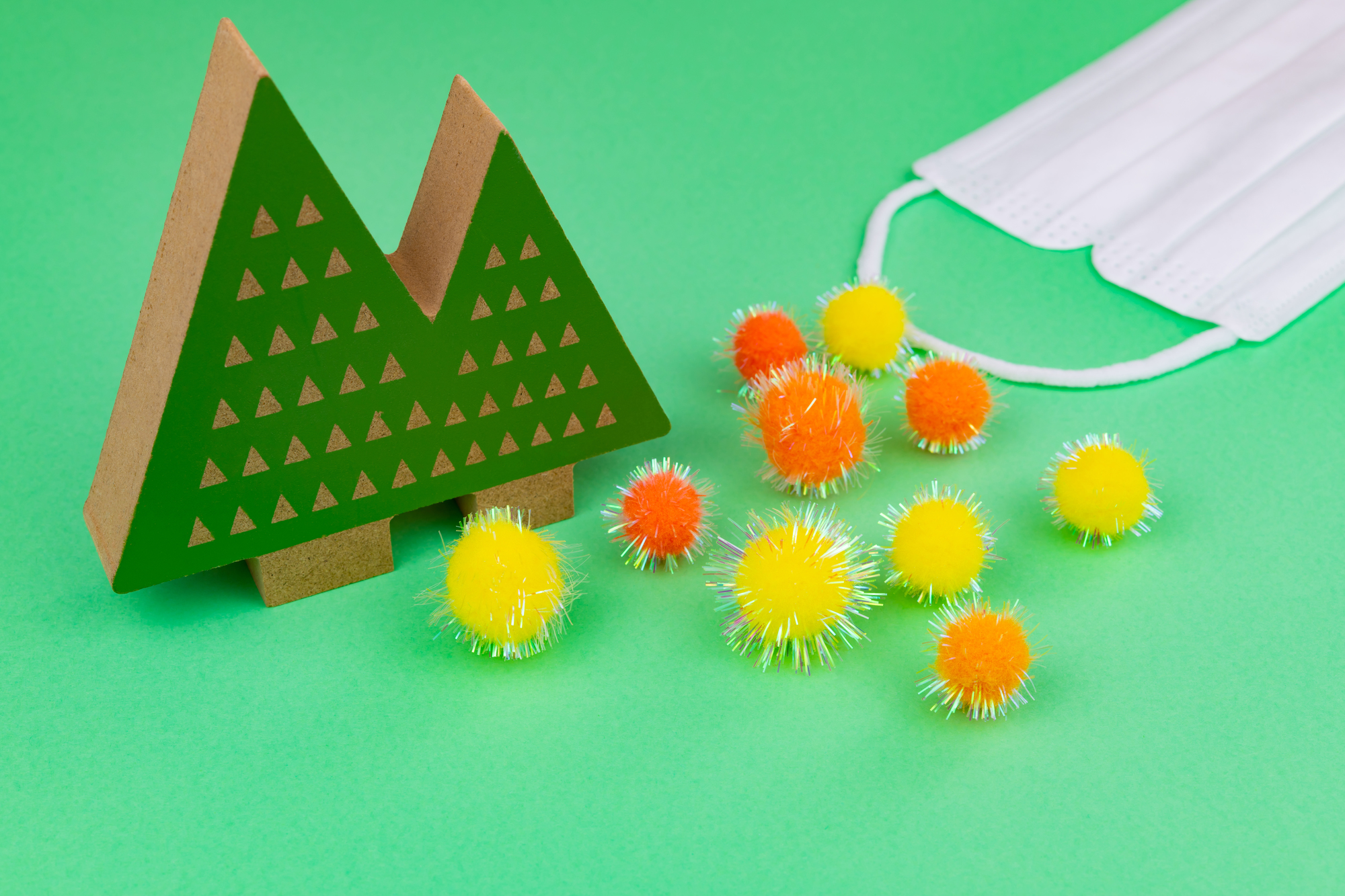
春になると、多くの人が悩まされる花粉症。国民の3人に1人がスギ花粉症にかかっているとされており、「国民病」といわれることもあります。
症状を抑えたり、罹患を防いだりするには、花粉症の症状が毎年出ている方はもちろん、まだ花粉症になっていない方も、早めに予防・対策を行うことが大切です。
ここでは、簡単に行える花粉症の対策方法をご紹介します。
目次
花粉症の原因は?

花粉症とは、樹木や草花の花粉が原因で、鼻水やくしゃみ、目のかゆみ、喉の痛みといったアレルギー症状が現れる病気のことです。
スギやヒノキが有名ですが、日本国内ではブタクサやヨモギ、シラカンバ(シラカバ)、イネなど、60種類ほどの花粉が花粉症を引き起こすとされています。
花粉症の症状は、原因となる植物の花粉が多く飛散する時期に見られるのが特徴です。スギやヒノキの症状が出るのは春なので勘違いすることもありますが、夏や秋にかけて花粉の飛散量が増える植物もあります。
特定の季節になると鼻水やくしゃみ、目のかゆみといった症状が現れる方は、花粉症の可能性があります。花粉の飛散時期と症状が出る時期を確認してみると良いでしょう。
花粉の飛散時期や飛散量の予測は、天気予報などでも提供されています。花粉情報を活用して、早めに花粉症対策を行うことが大切です。
【外出時】花粉症対策のポイント

花粉症の基本的な対策方法は、体内に侵入する花粉の量を減らすことです。花粉が体内に侵入しなければ、症状は和らぎます。花粉症の発症を予防する効果が期待できるのもメリットです。
外出を控えるのが一番ですが、花粉の時期は一歩も外に出ないで済ますというのは現実的ではありません。外出する際は、どのような対策を行えば良いのでしょうか。
1. マスクを着用する
花粉が飛散している時期に外出する際は、マスクを着用しましょう。マスクを着けるだけで、体内に侵入する花粉の量を減らすことが可能です。 一般的な市販のマスクでおよそ70%、花粉症用のマスクで84%ほど、花粉の侵入する量を減らすことができるとされています。衛生面や性能面から、使い捨ての不織布マスクを着用するのがおすすめです。
また、マスクの内側にガーゼを当てる方法でも、鼻から侵入する花粉の量を減らせることがわかっています。
2. メガネをかける
マスクだけではなく、メガネをかけるのもおすすめです。花粉症用のゴーグルではなく、通常のメガネをかけるだけでも、目に入る花粉の量は減少します。普段メガネをかけない方は、伊達メガネをかけるのも良いでしょう。
コンタクトレンズによる刺激がアレルギー性結膜炎を悪化させる恐れがあるので、日頃コンタクトレンズを使っている方も、花粉症の症状に悩む時期は、メガネをかけることをおすすめします。
3. 花粉が付きにくい服を着る
外出時に花粉が付着しやすい服を着ていると、服に付着した花粉が屋内に入ったり、体内に花粉が侵入したりする原因になります。ウールなどの花粉が付着しやすい服装は控えて、綿やポリエステルといった花粉の付きにくい衣類を選ぶこともポイントです。
衣類を着用しない頭や顔は、体の中でも花粉が付着しやすい部位です。つばの広い帽子をかぶって、頭に付着する花粉の量を減らすのも良いでしょう。
4. 帰宅したらうがいと洗顔を
外から帰宅したら、建物に入る前に体に付いている花粉を落としましょう。頭や衣類をはらって花粉を落とすことで、室内に侵入する花粉の量を減らせます。
衣類に付いた花粉を落とすだけでなく、うがいや洗顔を行うことも大切です。うがいによって喉に付着した花粉を、洗顔によって顔に付着した花粉を落とすことができます。
目や鼻の周囲に付いた花粉が体内に侵入し、かえって症状が悪化する恐れもあるため、洗顔は丁寧に行ってください。
また、市販の生理食塩水を使って鼻うがいを行い、鼻に入り込んだ花粉を洗い流すのも効果が期待できます。
【在宅時】家でできる花粉対策

どれだけ対策をしていても、室内への花粉の侵入をゼロにはできません。外出中だけでなく、在宅時も花粉対策は必須です。家に居る時は、次のような方法で花粉対策を行いましょう。
1. 換気の方法を工夫する
窓や扉を開けると、屋外を漂っている花粉が室内に入ってしまいます。花粉が多く飛んでいる日は、極力お部屋の窓を開けるのは控えるのがおすすめです。
とはいえ、花粉が飛んでいる日だとしても、室内の換気などで窓を開けることもあるでしょう。そのような時は、窓を大きく開けるのではなく、少し開ける程度にとどめるのがポイントです。 この時、カーテンを閉めた状態で窓を開けると、室内に侵入する花粉の量を減らせます。
また、花粉が多く飛んでいる日は、洗濯物を外に干すのも控えて、部屋干しで済ませた方が良いでしょう。
2. こまめに部屋を掃除する
どれだけ注意していても、換気の時に窓から入ってきたり、衣類や髪の毛に付着した花粉が持ち込まれたりして、室内には花粉がたまってしまうものです。
こまめにお部屋の掃除を行い、室内にたまった花粉の量を減らすことも心がけましょう。
換気を行った際に窓から流入した花粉は、カーテンにも多く付着しています。カーテンの洗濯を定期的に行うことも大切です。
花粉症の悪化を防ぐには?

花粉症の発症には、人の免疫機能が関わっているとされています。花粉症の症状を抑えたり、発症を防いだりするには、日頃から規則正しい生活習慣や適度な運動を心がけ、免疫機能を保つことが大切です。
ヨーグルトをはじめ、花粉症に良いといわれている食品はいくつかありますが、1種類の食材をたくさん摂取しても、症状が大きく良くなったり、悪くなったりすることはないと考えられています。バランスの取れた食事を心がけましょう。
鼻の粘膜を保つために、過度な飲酒や喫煙も控えることをおすすめします。
また、加湿器やスキンケア用品を活用して、肌の乾燥を防ぐことも大切です。花粉が肌に触れると、花粉性皮膚炎と呼ばれる皮膚トラブルにつながる恐れがあります。
肌を保湿して乾燥を防ぐことで、花粉が原因の皮膚トラブルを予防可能です。
花粉症の治療方法

花粉症の治療は、他のアレルギーの治療と同様に、症状が出る前か、発症早期の段階で治療するのが有効とされています。
花粉の主な治療方法は、対症療法と免疫療法の2種類に大きく分けられるため、違いを知っておくと役立ちます。
【対症療法】
抗ヒスタミン薬や鼻噴霧用ステロイド薬といった薬を使って、花粉症の症状を抑える治療法です。毎年花粉症の症状に悩まされている方は、花粉が飛散する1週間前までを目安に、薬を飲み始めると良いでしょう。
薬を使った治療では効果が得られない時は、レーザーで鼻の粘膜を焼いてアレルギー反応を抑える「レーザー手術」を行うこともあります。
【免疫療法】
花粉の成分が含まれた薬剤を定期的に投与して、花粉に体を慣れさせる治療法です。対症療法でも症状が改善しなかった人でも、効果を得られる可能性があります。治療終了後も、ある程度は効果が持続するのもメリットです。
一方で、副作用が出やすい、治療継続の推奨期間が長いなどのデメリットもあります。
症状緩和には早めの花粉対策が大切

花粉症は、日本人の多くが悩まされている季節性のアレルギー症状です。花粉症の症状を和らげたり、発症を防いだりするには、早めに予防・対策する必要があります。
ご紹介した方法を参照に、症状が悪化しないように気をつけてみてください。