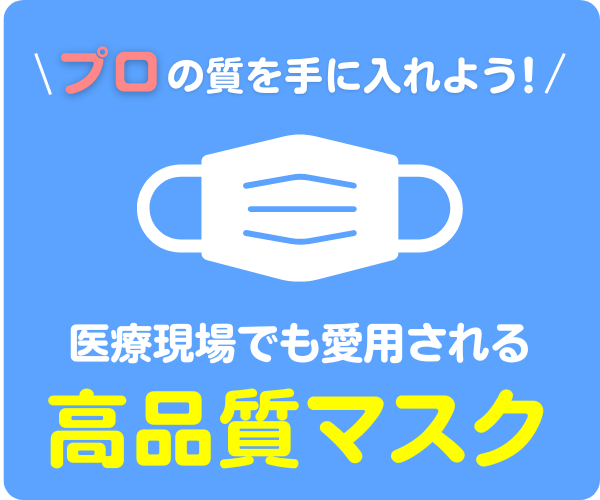入浴介助とは? 安全に行うための手順と注意点を知ろう

「入浴介助」は、介護の際に必要不可欠なケアのひとつです。できるだけ毎日入浴させるのが望ましいとはいえ、介護の中で特に負担がかかりやすいケアでもあります。浴室で足を滑らせて転んだり、溺れたりするリスクに注意しなければいけません。
入浴介助を安全に行うには、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。
ここでは、入浴介助を行うために必要な準備や、具体的な手順などをご紹介します。
目次
介護における入浴介助の目的
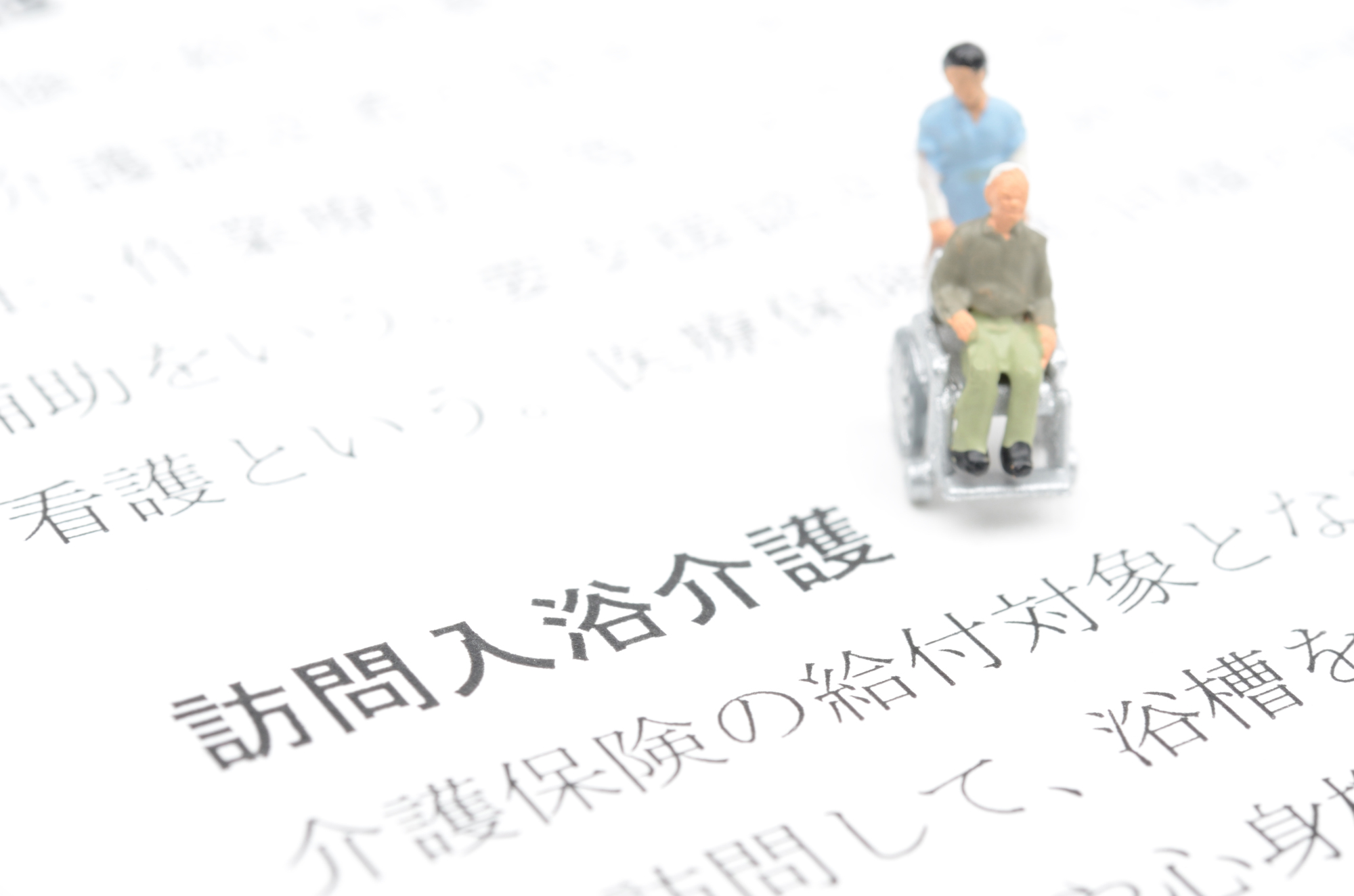
入浴介助とは、着替えや体を洗うなど、要介護者の入浴をサポートすることです。
入浴介助を行う目的としては、以下の2つが大きく挙げられます。
1. 体を清潔に保つ
入浴介助の一番の目的は、要介護者の体を清潔に保つことです。入浴をしないまま暮らし続けると、皮膚に付着した汚れや細菌がそのまま体に残り続けてしまいます。
床ずれや感染症などにつながる恐れもあるため、入浴によって体をきれいな状態に保つことは重要です。
また、衣類を脱ぐ入浴時は、要介護者の全身をチェックする数少ない機会でもあります。定期的に入浴介助を行うことで、外傷などの異変を早期発見できる可能性が高まる点もメリットです。
2. リラックス効果を得る
温かい湯船につかって体を温めると、血流が良くなり新陳代謝も高まります。筋肉の緊張をほぐしたり、リラックスしたりする効果も期待できます。
体を清潔に保つだけでなく、日常生活を気持ち良く過ごすためにも、入浴介助は欠かせないものといえるでしょう。
入浴介助前に必要な準備

入浴には多くのメリットがある反面、浴室で転んだり、浴槽で溺れたりするリスクも付きまといます。安全かつ快適に入浴介助を行うには、入念な事前準備が欠かせません。
入浴介助を行う前に必要な準備や、チェックしたいポイントをご紹介します。
1. 適切な入浴方法を把握する
湯船につかる、シャワーを浴びるなど、入浴の方法はいくつかの種類に分けられます。要介護者の体の状態などに応じて、適切な入浴方法を選択することが大切です。
例えば、自力で歩くことができる人や、手すりをつかんだ状態で歩ける人は、極力要介護者本人で体を洗ったり、湯船につかったりする「一般浴」を行うようにしましょう。
座っている状態なら姿勢を保つことができる場合は、中間浴(リフト浴)や、専用の椅子・ストレッチャーを用いる機械浴を行うのが有効です。
また、体調によっては、湯船につかるのが難しいことも考えられます。シャワーで体を洗うシャワー浴にとどめたり、温かいタオルで体を拭いたりする方法も選択肢として検討しましょう。
2. 要介護者の体調や皮膚を確認する
体調が優れない時に入浴した結果、体調が悪化してしまう可能性があります。入浴を行う前に、血圧が普段よりも高くないか、発熱していないか、脈拍や呼吸に異常がないかなど、要介護者の体調を必ず確認してください。
何らかの異常が見られる時は、湯船につかるのは控えて、タオルで体を拭くだけにとどめるなど、別の方法を検討するのがおすすめです。
前述のとおり、入浴時は衣類を脱ぐため、普段は見ることができない部分を目視できる数少ないタイミングでもあります。
傷や乾燥、湿疹、赤みなどの異常がないかどうかも、忘れずに確認しておきましょう。
3. 浴室や脱衣所を温めておく
浴室や脱衣所を事前に温めておくことも大切です。急激な温度差によって血圧が上下し、体に負担がかかる「ヒートショック」を予防しやすくなります。
特に、外気温が低い冬場はヒートショックが起こりやすいので注意しましょう。脱衣所に暖房を設置する、シャワーのお湯を浴室の壁にかけて温めておくなどの対策を行うのがおすすめです。
4. 入浴に必要なものをそろえる
入浴中・入浴後に必要なものは、事前にそろえておくことも大切です。入浴中に足りないものを取りに行こうと目を離した隙に、事故が起こる可能性があります。
入浴中や入浴後に必要なものの例は、以下のとおりです。
・要介護者向けに必要なもの:柔らかいスポンジ、ボディソープ、シャンプー、シャンプーハット、着替え、軟こう、保湿剤 など
・介護者が使用するもの:滑りにくいサンダル、手袋、エプロン など
また、浴室内でも使えるシャワーキャリーやシャワーチェアー、転倒防止用のマット、浴槽の手すり、バスボードなど、入浴を補助する介護用品を用意しておくのもおすすめです。
入浴介助の流れとポイント

1. 入浴前の介助
前述のとおり、入浴中の思わぬ事故や要介護者の体調悪化などを防ぐには、入浴前の準備が重要です。入浴前は、以下の流れで介助を行うと良いでしょう。
1. 要介護者の体調を確認する
2. 浴室や脱衣所を温める
3. 浴槽にお湯を張り、必要なものをそろえる
4. 要介護者にトイレを済ませてもらい、脱衣所に移動する
要介護者の中には、温度を感じにくい方もいらっしゃいます。湯船のお湯が熱くなりすぎないように注意してください。体調や持病の有無などにも左右されますが、お湯の温度は40℃程度が目安です。
また、脱水症状や熱中症を防ぐために、入浴前に水分補給をしてもらいましょう。
2. 入浴中の介助
入浴中に体を洗う手順は、以下のとおりです。ただし、ご紹介する方法はあくまでも一例です。要介護者の希望も聞きながら、体を洗う手助けを行ってください。
1. シャワーチェアーにお湯をかけて温める
2. シャワーチェアーに座ってもらい、足元から徐々にお湯をかける
3. 髪⇒上半身⇒下半身の順に体を洗う
4. 体を洗い終えたら、ゆっくりと浴槽に入ってもらう
5. 5分ほどしたら、足元に気をつけながら浴槽から出る
お湯は、心臓から最も遠い足元からかけるのがポイントです。お湯をかける前に、声掛けも忘れずに行いましょう。シャワーは突然お湯の温度が変わることがあるため、介助者が常にお湯に触れて温度を確かめておくと安心です。
また、体を洗う際は、肌を傷つけないように優しく洗うことを心がけてください。
3. 入浴後の介助
入浴が終わって湯船から出たら、以下の手順で介助を行うと良いでしょう。
1. 体の水分をタオルでしっかりと拭き取る
2. 椅子などに腰かけてもらい、ゆっくりと着替えを行う。必要な場合は軟こうや保湿剤などを塗る
3. 水分補給をしてもらう
4. 体調を確認する
足の裏がぬれたままだと、滑って転倒するリスクが高まります。入浴後は、最初に足の裏を丁寧に拭いておくと安心です。
また、入浴すると汗をかきます。脱水症状を防ぐために、しっかりと水分を飲んでもらうこともポイントです。
入浴介助で注意したい点

入浴中は、命に関わる事故が発生する可能性もあります。入浴介助を安全かつ快適に行うためには、以下の点に注意が必要です。
1. プライバシーに配慮する
人によっては、家族に自分の裸を見られることにも抵抗感を感じることがあります。要介護者のプライバシーに配慮して、入浴介助を行ってください。
カーテンやドアを閉めて他人に見えないようにする、声掛けをしてから介助を行うといった気配りは必須です。
また、手の届く範囲は自分で洗ったり、拭いたりしてもらうなど、できることは自分でやってもらいましょう。自分で何かをすることがリハビリとなり、生活機能の維持にもつながります。
2. 安全に配慮する
床がぬれている脱衣所や浴室は、転倒のリスクが高い場所です。リフォームして手すりを用意する、転倒防止マットを敷いておくなど、転倒防止対策も欠かさずに行う必要があります。
前述のとおり、浴室内はヒートショックの危険性もあります。急激な温度変化を防ぐための対策も欠かせません。
また、入浴は思いの外体力を消耗します。体調が優れない時は控えることも大切です。
3. 長時間の入浴は控える
長時間の入浴は、のぼせやめまい、熱中症、脱水症状などの原因になる可能性があります。長時間の入浴を控えることも大切です。
湯船につかる時間は、5分程度を目安にすることをおすすめします。
安全を第一に考えることが大事

清潔さを保つために欠かせない入浴ですが、転んだり、溺れたりといった事故が起こるリスクがあります。体調悪化につながる恐れも捨てきれません。
入浴介助は、要介護者の安全を第一に考え、正しい方法で行うことが大切です。浴室内で使える介護用品も積極的に活用して、入浴介助を安全に行いましょう。