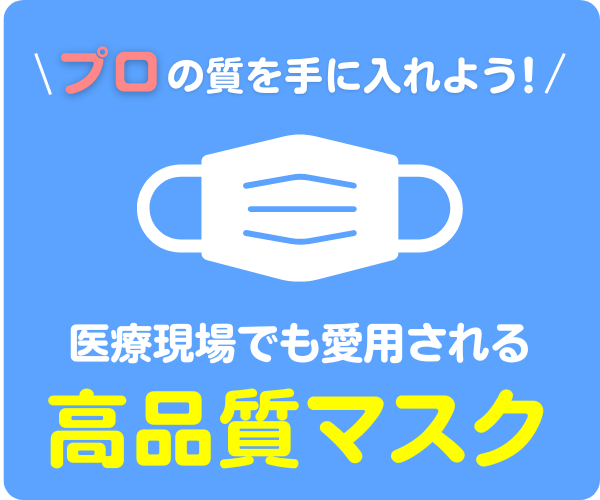在宅医療とは? 注目を集める医療の3つ目の選択肢を知っておこう

少子高齢化が進む日本において、病気や加齢によって通院が難しくなった時の選択肢として、近年注目を集めている医療のあり方が「在宅医療」です。
とはいえ、あまりなじみのない在宅医療に対して、金銭的・精神的な負担がどれくらいかかるのかなど、不安に思われる方は多いかもしれません。
ここでは、在宅医療を受けるための必要な費用など、知っておきたい基礎知識をご紹介します。
目次
在宅医療とは

自宅や老人ホームといった「患者が生活をしている場所」に医師や看護師などが訪問して、患者の診察・治療・健康管理などを行うのが在宅医療です。
医師や看護師をはじめ、歯科医師、薬剤師、理学療法士、訪問看護師など、多くの職員が連携して、患者の治療や介護を行います。
「病院よりも受けられる治療が限られるのでは」と不安に思われるかもしれませんが、専門職がチームを組んで患者に関わることで、自宅での治療や検査の実施を可能にしています。クリニックにもよりますが、酸素療法や点滴、人工透析、血液検査、リハビリテーション、口腔ケアなどを、自宅にいながら受けることも可能です。
また、在宅医療は定期的に医師や看護師が訪問して診療を行う「訪問診療」と、患者または家族からの依頼で医師が訪問する「往診」に大きく分けられます。
在宅医療を受けるための条件は?

在宅医療は、病気やけがなどが原因で通院するのが困難な方なら、基本的には誰でも、どのような疾患でも受けることができます。高齢者向けのサービスというイメージを持たれがちですが、子どもを含めた全ての年代の方が対象です。
在宅医療を受けられる例としては、以下のような方が挙げられます。
・足が不自由で外出や通院が難しい方
・障害があり、呼吸や排泄といった日常生活で医療的なケアが必要な方
・退院後、自宅での療養が必要になった方
・寝たきりとなり、自宅での介護または看護が必要な方 など
在宅医療にかかる費用

ただし、具体的な金額は保険の種類や訪問先、訪問回数、疾患、患者の状態などによって異なります。詳細は、市区町村や医療機関にお問い合わせください。
1. 訪問診療代、臨時で必要な医療費・薬代
通院と同様に、在宅医療も医療保険の対象です。自己負担の割合も通院と同じで、年齢または収入によって1~3割です。
また、負担額が一定額を超えた時は、申請すると負担金が戻ってくる「高額療養費制度」も使用できます。
2. 介護サービスにかかる代金
訪問介護または看護、リハビリテーション、訪問入浴看護、デイサービス・デイケア、福祉器具レンタルなど、介護サービスにも費用がかかります。
とはいえ、こちらも介護保険を活用可能です。要介護認定のレベルによって支給限度額やサービスは変わるものの、支給限度額の範囲内であれば、原則は1~3割の自己負担金で介護サービスを利用できます。
限度額を超えたものに関しては全額自己負担となりますが、介護にも「高額介護サービス費制度」と呼ばれる自己負担限度額の制度が設けられています。申請することで負担金が戻ってくるため、活用してみてはいかがでしょうか。
3. その他
在宅医療は、自宅で診療や介護を受けることになります。光熱費や食費、おむつのような消耗品の購入費、自費診療費などがかかる点に注意が必要です。
患者の状態によっては、在宅医療に備えて自宅の環境を整えるためのリフォーム代がかかることも考えられます。
ただし、介護リフォーム代も、工事費用に対して補助金の支給を受けられます。患者の状態に左右されるとはいえ、通院するよりも金銭的な負担は抑えられるケースが多いです。
「自宅で医療を受けられる」以外の在宅医療のメリット

在宅医療は、自分の家で適切な医療を受けられる制度です。通院と比較して、どのようなメリットを得られるのでしょうか。
1. 患者や家族の負担を軽減できる
在宅医療では、通院・入院することなく、住み慣れた自宅で医師や看護師による適切な医療を受けられます。
入院中は多くの方と一緒に生活するため、周囲に気を配らなければいけません。家族と離れて暮らすことが、ストレスになる可能性もあります。
一方で、在宅医療なら、いつもの場所で生活しながら専門的なケアを受けることが可能です。通院する必要がなくなるので、通院時の介助や介護の負担軽減にもつながります。
患者本人だけではなく、介護を行っている方の負担を減らすうえでも、在宅医療は有効です。
2. 医師との関係性を深められる
医師や看護師が自宅に訪問して専門的なケアを行う在宅医療は、かかりつけ医としての役割も果たすことになります。
一般的な通院・入院よりも患者や家族と医師の距離が近く、深い関係性を築きやすい点もメリットです。患者の普段の様子を見たり、家族の持つ悩みを把握したりしながらサポートを行うことができます。
ただし、在宅医療は医師や看護師に自宅に来てもらわなければいけません。さまざまな治療や検査を受けられるとはいえ、医師が常駐して設備も整っている病院に比べると、行える医療行為には限界があります。 また、緊急時に医師がすぐに駆け付けるのが難しい点にも注意が必要です。
在宅医療を行っている医師の探し方

在宅医療で適切なサポートを受けるには、在宅医療を依頼する医師(クリニック)の探し方が大切です。在宅医療を希望している方は、以下のポイントを意識して医師を探してみると良いでしょう。
1. 自宅からの距離
訪問診療を行える範囲は、医療機関から16km以内(車で片道20分程度)と定められています。
入院と異なり、在宅医療は緊急時にすぐ対応してもらうのが難しいことも考えられます。できるだけ自宅から近く、素早く対応してもらえる可能性が高いクリニックを選ぶことが大切です。
2. 対応している疾患
対応している疾患や、ケアの内容の確認も必須です。医療機関だからといって、全ての疾患に対応できるわけではありません。場合によっては、希望するケアを受けられないことも考えられます。
患者の状態に適したクリニックを選ぶようにしましょう。
3. 対応している時間
在宅医療を行っている時間も確認しておきましょう。24時間365日、昼間のみなど、クリニックによって対応している時間は大きく異なります。
24時間対応ではないクリニックに在宅医療を依頼する際は、緊急時はどこに連絡すれば良いのか事前に決めておくことが重要です。
4. 医師との相性も重要
医療従事者も、患者や家族と同じ人間です。医師の診療方針や人柄が合わないと、さまざまなトラブルにつながる恐れがあります。医師との関係性を深めやすいという在宅医療のメリットは、デメリットにもなる可能性がある点に留意しておきましょう。
在宅医療を円滑に進めるために、医師と患者や家族の相性を確認しておくと安心です。
患者や家族の気持ちを確認しておこう

在宅医療は、あくまでも患者やその家族が納得したうえで行うものです。家族が無理をしてしまうと、在宅医療自体が成り立たなくなる可能性があります。
患者本人が本当に自宅での医療を希望しているのか、家族全員が在宅医療に納得しているのかなど、お互いの気持ちをよく確かめておきましょう。
事前に気持ちを確かめておくことで、在宅医療の開始後にトラブルが起きるリスクを軽減できます。
早めの準備が在宅医療の鍵

通院や入院に代わる選択肢として注目を集めている在宅医療は、患者や家族の意思を重視しているのが特徴の制度です。各種サービスやサポートを活用すれば、通院や介護など、さまざまな負担を軽減できる可能性があります。
ただし、在宅医療にはメリットだけでなく、注意したい点もあります。在宅医療に関する知識を蓄えて、早めに準備をしておくことが大切です