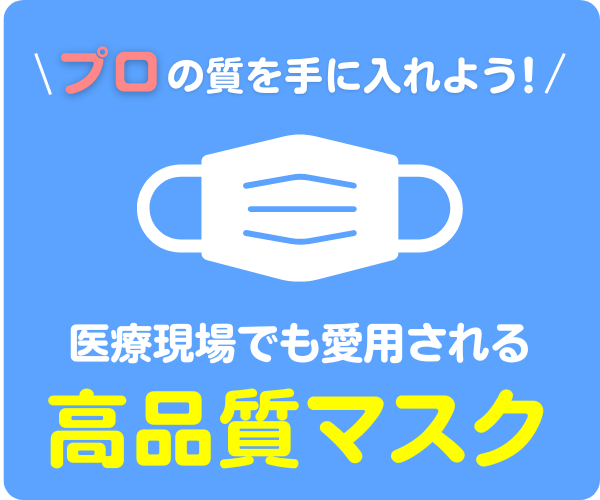在宅介護で欠かせない「トイレ介助(排泄介助)」の注意点

トイレ(排泄)は、人が生きていくうえで不可欠な行為です。トイレへの移動や排泄などを手伝う「トイレ介助(排泄介助)」は、介護において重要なケアのひとつといえます。
しかし、排泄はプライバシーに関わる行為でもあります。介護をする人はもちろん、介護を受ける人にとっても大きな負担になるものです。そのため、排泄介助を行う際は、さまざまな点に配慮する必要があります。
ここでは、在宅介護の際に重要な、排泄介助のポイントや注意点をご紹介します。
目次
要介護者に適した排泄方法の選び方

トイレ介助と一口にいっても、具体的な方法はいくつかの種類に分けられます。トイレ介助の方法と、それぞれの特徴を知って、要介護者に適した方法を検討することが大切です。
1. トイレ
要介護者と一緒にトイレに移動して、トイレ介助を行う方法です。要介護者の状態によって、一緒に歩いて移動する、車いすで移動する、移動から排泄まで全てを介助する、一部のみ手助けするなど、具体的な方法は変わります。
また、足腰が弱くなっている高齢者の方は、排泄時にしゃがむ必要がある和式トイレの使用が難しいことが考えられます。自宅が和式トイレの方は、安定して座りながら排泄が行える洋式トイレにリフォームするのがおすすめです。
2. 介護用トイレ(ポータブルトイレ)
介護用トイレ(ポータブルトイレ)とは、持ち運び可能で、ベッドの横などに置いて使用できるトイレのことです。トイレまで歩く必要がないため、ある程度の距離を移動するのが難しい方や、夜中に何度もトイレに起きる方に適しています。
介護用トイレによっては、座面の高さ調整機能や肘掛け、柔らかい座り心地のソフト便座、暖房機能、シャワー洗浄など、便利な機能を搭載しているのも特徴です。
衛生を保ったり、臭いを防いだりするために、排泄物の処理や便器の清掃を定期的に行う必要があり、手間がかかりやすい点は留意してください。
歩行器や車いすなどと違い、介護用トイレは肌が直接触れることになります。そのため、介護用トイレは衛生上の観点からレンタルできません
ただし、特定福祉用具購入費の支給対象になるため、購入する際は介護保険を利用可能です。
3. 差込便器・尿器
ベッドから立ち上がったり、座ったりすることができず、一般的なトイレや介護用トイレで排泄するのが難しい方向けの方法です。ベッド上で、差込便器や尿器を使って排泄の介助を行います。
介助があれば、姿勢を変えることはできる場合に適しています。可能な限り、自分で容器を使って排泄してもらうことがポイントです。
4. おむつ
下腹部に着用して、そのままおむつに着用する方法です。便意または尿意を感じるのが難しい方や、排泄を本人の意思でコントロールできない方に適しています。
介護用のおむつには、パンツ式やテープ式などの種類があり、それぞれ特徴が異なります。
パンツ式は、一般的な下着と同じように履くことができるため、トイレや介護用トイレを利用できる要介護者の方におすすめです。
一方で、テープ式は腰を上げなくても交換などの介助を行えます。寝たきりで体を動かすのが難しい要介護者の方には、テープ式のおむつを用意すると良いでしょう。
衛生面や臭いの問題につながるため、おむつは定期的に交換を行い、清潔な状態を保つことが大切です。
トイレ介助の基本の流れ

トイレ介助は、事前に基本的な流れや手順を把握しておくと、スムーズに行いやすくなります。安全にトイレ介助を済ませるために、基本の流れを覚えておきましょう。
要介護者がトイレまで移動できる場合と、介護用トイレを使用する場合の2パターンに分けて、介助の基本の流れをご紹介します。
1. トイレまで移動できる場合
トイレに移動できる時は、要介護者のペースに合わせて、できるだけ自分でできることは任せることがポイントです。
【介助の手順】
1.トイレに移動する
障害物の有無を確認した後、必要に応じて手を貸しながらトイレに移動します。移動の際は要介護者のペースに合わせることが大切です。
2.脱衣
ズボンやパンツなどを脱がせます。全てを手助けするのではなく、できることは本人に任せましょう。介助を行う時は、手すりを持ってもらってから衣服を降ろしてください。
3.便座に腰かける
手すりがある場合は、転倒に注意しながら、手すりを持った状態で座ってもらいます。要介護者が腰かけた後は、足がしっかりと床についているか確認してください。
4.排泄する
排泄中は、介護者はトイレの外で待つのが基本です。トイレの鍵はかけずに開けておき、何かあった時にすぐ対応できるようにしましょう。
事前に、終わったら声を掛けて欲しいと伝えておくことも重要です。
5.清拭
本人が自分で拭き取ることができない時は、腰を支えながら臀部を少し上げてもらい、介護者が手早く拭き取ります。自分でできる場合は任せるのが基本です。
2. ポータブルトイレを使用する場合
トイレまで移動するのが難しい時は、ポータブルトイレを利用しましょう。ポータブルトイレを使用する際の流れは、以下のとおりです。
【介助の手順】
1.トイレの準備
トイレの前に、ポータブルトイレのバケツにトイレットペーパーを敷いておきましょう。汚れが付きにくくなり、後処理の手間を省けます。
2.移動
トイレの準備が済んだら、要介護者の体を支えながら、ポータブルトイレまで移動します。
その後は、脱衣・トイレに腰かける・排泄・清拭と、一般的なトイレを使う場合と同じ手順で排泄を済ませます。
排泄を済ませたら、介護トイレの処理を行ってください。そのまま放置すると臭いの原因になるため、排泄後は早めに処理することが大切です。
トイレットペーパーで汚れを拭き取り、トイレに排泄物を流したら、トイレブラシや洗剤を使ってきれいに清掃を行いましょう。
トイレ介助を行う時のポイント

排泄は、生命を維持するために欠かせない行為であると同時に、個人的でデリケートな行為でもあります。介助の方法次第で、相手を傷つけたり、不快感を与えたりする恐れも捨てきれません。
トイレ介助を行う際は、以下の点に注意が必要です。
1. 安全に配慮する
高齢になり、足腰の筋肉が衰えると、トイレまでの移動や立ち座りといった動作に影響が現れます。介助を行う時は、移動中や排泄時の安全に配慮することが重要です。
滑りやすい履物の使用は控える、手すりにつかまってもらう、床に障害物となるものを置かない、段差をなくすなど、部屋からトイレまでの移動中に転倒しにくい環境を整えてください。
トイレ内では、体勢が崩れないように手すりをしっかり握ってもらうことがポイントです。トイレ内や廊下に手すりがない場合は、リフォームで取り付けておくと良いでしょう。
2. できることは自分でしてもらう
要介護者の状態にもよりますが、1から10まで、全てを介助する必要はありません。トイレへの移動や衣類の上げ下げ、立ち座り、排泄後の処理など、本人が自分でできることがあるなら、極力自分でしてもらいましょう。
生活機能の維持だけでなく、要介護者の自尊心を保つことにもつながります。
3. プライバシーに配慮する
排泄を他人に手伝ってもらうことは、誰でも羞恥心を感じるものです。トイレ介助の際は、要介護者が不快に思わないように、介護者の方も配慮する必要があります。
必要に応じてタオルで下腹部を覆って隠す、介護用トイレの周囲を間仕切りで囲う、排泄後は消臭剤で臭いを防ぐなど、プライバシーを守る意識を持つことも大切です。
4. 本人のペースに任せる
要介護者のペースに任せて、落ち着いて排泄できる環境を整えることも重要です。トイレ介助は、介護を行う人にとっても負担やストレスのかかるものです。
だからといって、排泄をせかしたり、失敗を責めたりすると、相手の自尊心を傷つけてしまいます。介助される側も羞恥心を持っていることを考慮した行動を心がけましょう。
5. 水分摂取を制限しない
排泄を失敗してしまった要介護者の中には、トイレの頻度を減らそうと水分摂取を控える方も見られます。水分摂取量が足りないと、脱水症状や便秘などの原因になりかねません。場合によっては、命に関わる恐れもあります。
水分摂取量が減ることの重大性を理解して、要介護者には必要十分な量の水分を飲むことを促してください。
要介護者に適したトイレ介助を行おう

適切なトイレ介助は、要介護者の生活の質を高めることにつながります。介護を行う方は、適切な方法でトイレ介助を行うことを心がけましょう。
介護者・要介護者ともに負担がかかりやすいため、適切な介護用品を用意しておくと安心です。
また、トイレ介助は、介護が必要になった本人も申し訳なさや恥ずかしさを感じていることが多いものです。相手の気持ちに寄り添い、無理のない範囲で本人に任せてみることをおすすめします。